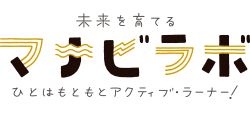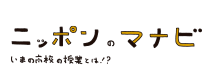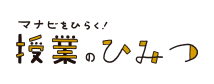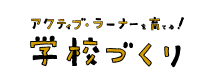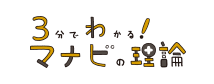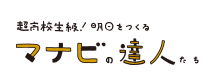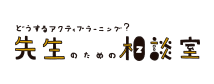第19回
2017.07.19
B.バーンスティン 「見えるペダゴジー」と「見えないペダゴジー」
3時間じゃ到底わからない!マナビの理論 解説編
特別企画「3時間じゃ到底分からないマナビの理論」では、教育をめぐる様々な理論・思想を紹介しつつ、3時間にわたる徹底討論をお送りいたしました。
今回は、そんな議論のなかで紹介された一節を取り上げて、少し踏み込んだ解説をしていきたいと思います。
3時間企画をご覧になった方も、これからの方にも、マナビの理論をめぐる論争を読み解くてがかりにしていただければ幸いです。
今回深読みしたい一節は、ゲストとしてご登場いただいた東京大学教育学研究科教授の小玉重夫先生のご著作『学力幻想』(ちくま新書)からの一節です。
ペダゴジーとは、過去を代表する大人世代と未来を代表する子ども世代という別の意味世界を生きるものの間の境界を架橋し、「子ども」から「大人」への移行を果たさせるための方法である。
小玉重夫『学力幻想』ちくま新書, 2013, p.112
まず、目に付くのは「ペダゴジー」という語です。一般的には、「教授法」や「教育方法」あるいは「教育学」と訳されますが、ここではあえてそうした訳があてられていません。
3時間企画では詳しく言及されておりませんでしたが、実は「ペダゴジー」の概念はバージル・バーンスティンによる独自の理論を下敷きにして提起されたものであったために、あえて「ペダゴジー」という表記がとられていたという経緯があります。
ですので、上述の一節を理解するために、少し回り道をしてバーンスティンの「ペダゴジー」の概念を確認しておきたいと思います。
バージル・バーンスティン(Basil Bernstein, 1924-2000)はイギリスの社会学者なのですが、教育を通じて学力格差がいかに再生産されるのかを言語コードに着目して理論化したことで教育学においても広く知られています。
バーンスティンは、ペダゴジーを狭義の教授法に還元されるものではなく、「文化の生産と再生産の基底をなす実践」を指す概念として用いています。その上で、彼はペダゴジーという語に対して二つの概念区分を設けています。
それが、3時間企画でも論点になった「見えるペダゴジー」と「見えないペダゴジー」という区分です。簡単にその意味するところを整理すると以下のようになります。
「見えるペダゴジー」:学習内容や進度が厳格に定められ、教授者の意図や評価基準が見えやすい教授のあり方。
「見えないペダゴジー」:子ども中心主義的で、教授者の意図が容易には見えにくい教授のあり方。たとえば、教科横断的カリキュラムや総合学習などはこうした側面が大きい。
「見えるペダゴジー」が伝統的な教授モデルと整合的なものであるのに対して、「見えないペダゴジー」は子どもの関心や意欲を重視した進歩的で民主的な教授のあり方と親和的なものとして捉えることができます。
しかし、バーンスティンの研究の主眼は、一見民主主義的であるように思われる「見えないペダゴジー」によって、かえって階級間の学力格差が拡大、再生産されているという点にあります。
同様の研究結果は日本においても報告されています。こうした成果をふまえると、階層差を縮めるという点ではむしろ「見えるペダゴジー」が有効かもしれないという仮説にもうなずける部分があるのではないでしょうか(耳塚寛明ほか「先鋭化する学力の二極分化–学力の階層差をいかに小さくするか」『論座』2002年11月号)。
特別企画でも論点になりましたが、こうした指摘は、今日の「アクティブ・ラーニング」の視点に立った教育課程の改善に対しても批判的な視座をもたらすものでもあります。
アクティブ・ラーニングの理論においては、知識偏重型の教授モデルが批判され、学習者の能力(コンピテンス)発達に強調点が置かれる傾向があります。
しかし、実はこうした能力発達は一元的な達成基準では評価しにくいために、能力発達は教師の主観に委ねられる部分も多く、ことによればそうした評価の背景にある文化的、社会的な背景が隠蔽されつつ再生産されることも起こりうるということになります。全国調査の結果を見てみますと「生徒の学習活動を客観的に評価することが難しい」ことが先生方の悩みの上位に挙げられていますが、こうした結果も「見えないペダゴジー」の問題と無関係ではないでしょう。
さらに、いわゆるアクティブ・ラーニング型の授業が子どもの学習意欲や関心に依存しがちであることにも注意が必要です。というのも、バーンスティンらの再生産論を敷衍すると、学習への意欲や関心が高い子どもとそうでない子どもといった具合に、能力発達の成果を個人や家庭に帰責することが、その背後にある社会的、政治的な構造を覆い隠す傾向を助長するとも考えられるからです。
さて、このように「見えるペダゴジー」と「見えないペダゴジー」という概念区分を参照すると、格差の縮小という点では伝統的な教授法への回帰が有効な路線であるように思えてきます。
しかしながら、単に「見えるペダゴジー」へと回帰するのでは、一見、格差自体は縮小しているように見えても、それは一元的な価値観や評価基準の共有を前提とした「縮小」にすぎません。
したがって問題は、伝統的な教授法への回帰ではない形で、「見えるペダゴジー」を再構成していくという点にあります。バーンスティン自身もその路線で模索していたふしがあるものの、実際にはバーンスティンが示した可能性は、ジル・ボーンによって「ラディカルな見えるペダゴジー」として定式化されています。
ボーンによれば、「見えるペダゴジー」が個人の変容をペダゴジーの目的としているのに対し、「ラディカルな見えるペダゴジー」は社会関係の変容をペダゴジーの目的としている点で大きく異なるといいます。
個人間の競争を前提として結局は階梯的な序列化に帰結する「見えるペダゴジー」への回帰ではなく、社会における自分自身の位置を理解し、社会集団間の関係を理解する(見える化する)ことを通じて、社会関係自体の組み換えを射程にいれた(ラディカルな)、文化の生産と再生産の実践としてペダゴジーを再構築していくというのがボーンのねらいです。
さて、ここでようやく冒頭でご紹介した小玉先生のご著作からの一節に込められた含意が見えてきます。
バーンスティン、ボーンの理論枠組みを参照しつつ、小玉先生はそれを子どもと大人の間にあるギャップの問題へと敷衍して議論を展開されています。
「見えるペダゴジー」が大人(教授者)の権威を前提とした、垂直的な大人-子ども関係によって成り立っているのに対して、「見えないペダゴジー」は大人(教授者)の権威性を隠蔽することで成り立っている。
それに対して、「ラディカルな見えるペダゴジー」は、大人と子どもそれぞれの意味世界の差異を前提としながらも、その差異を固定化するのでも見えなくするのではなく、理解し架橋することで両者の関係性を組み換える実践として捉えられています。
前述した格差の問題に加えて、大人-子ども、教師-生徒、教え-学びの関係性自体の問い直しが、アクティブ・ラーニングのこれからを考えていく際の重要な視点になるのではないでしょうか。
「特別編 3時間じゃ到底分からないマナビの理論」はこちら→
-
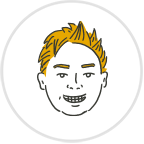
取材
田中 智輝
-

撮影
松尾 駿